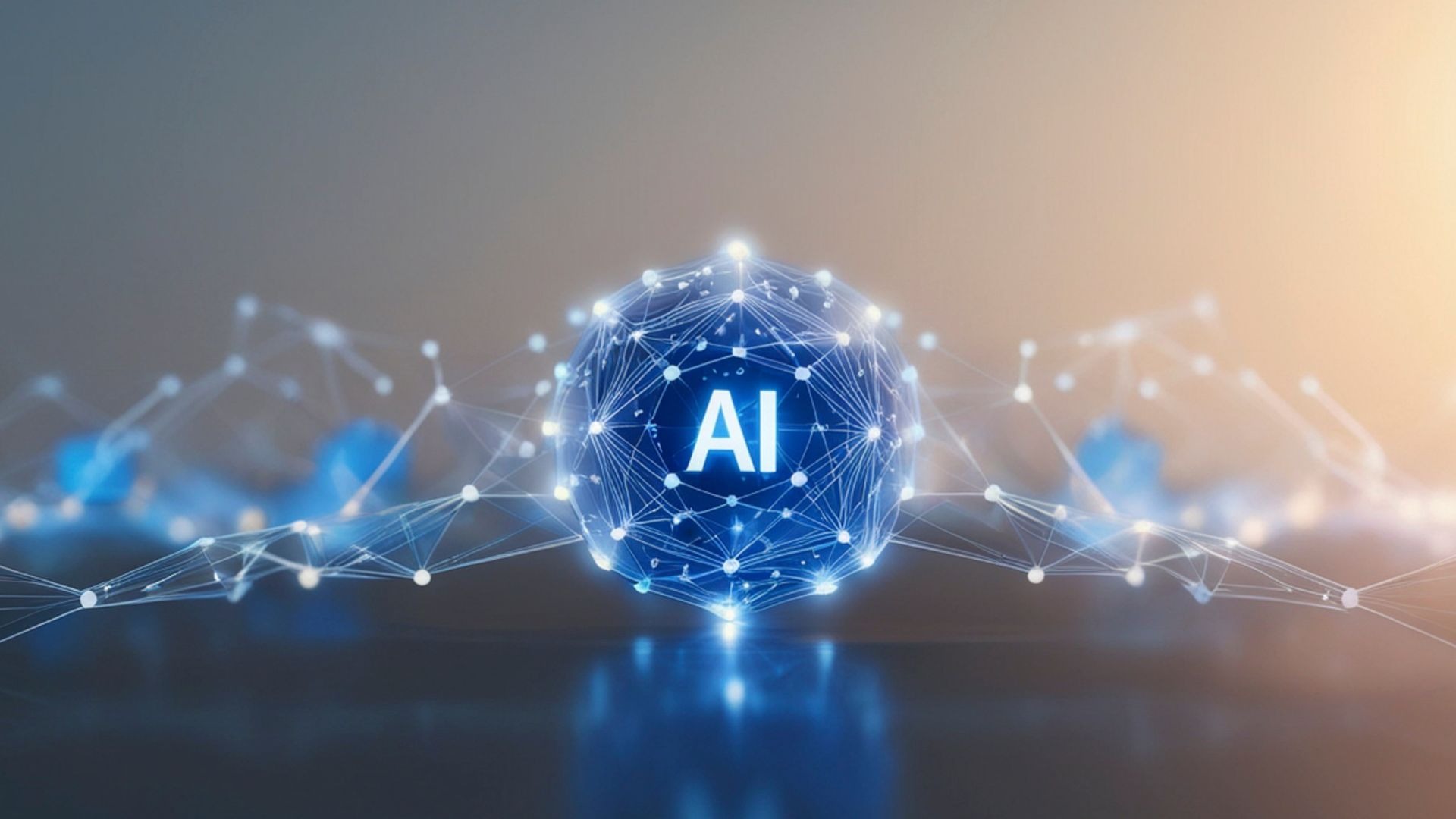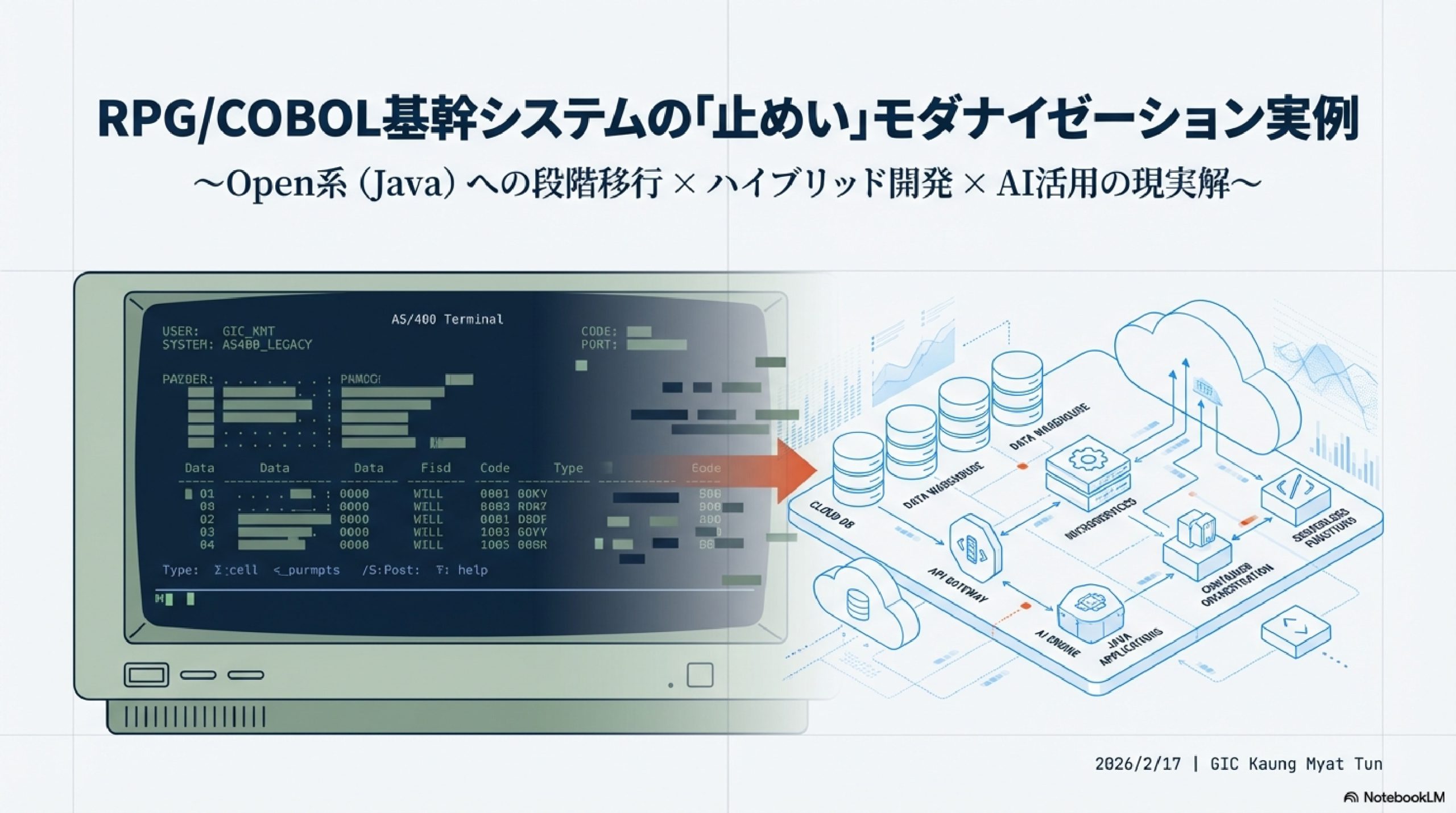要約
- 2019–20年に約91万人だった受験者数は、2023–24年に約12.9万人まで急減。2024–25年は再試験を含め約20.8万人。
- 背景には、治安悪化・教員離散・徴兵回避・2025年大地震など需要/供給の同時ショック。
- 企業と大学は、学歴証明の困難を前提に、評価の仕組みをアップデートする必要があります。
- マトリ試験とは
ミャンマーの「マトリ試験(Matriculation / University Entrance Examination)」は、高校最終学年が受ける全国統一試験で、大学進学の主要ルートです。新カリキュラム(KG+12)移行後も、大学入学資格としての位置づけは継続しています。2021年以降の社会情勢により、試験の実施・運営や受験行動に大きな影響が生じています。
- データで見る:受験者数の推移(近年)
- 2018–19:約85万人
- 2019–20:約91万人
- 2020–21:中止(COVID-19の影響)
- 2021–22:約28万人
- 2022–23:約16万人
- 2023–24:約12.9万人
- 2024–25:約20.8万人(3月のM7.7地震による答案焼失で約6.2万人が再試験を受験)
ポイント:2019–20 → 2023–24で約**−78%**。2024–25は再試験の特殊事情で一時的に持ち直したものの、構造的な回復トレンドとは言い切れない状況です。
- なぜ受験者が減ったのか(背景要因の分解)
3-1. 需要側ショック:受験回避の増加
- **治安悪化・国内避難(IDP)**により、通学・受験そのものが困難に。
- **人民兵役法(徴兵制)**の施行で、若年層の国外流出・国内避難・進学中断が加速。
- 家計へのインフレ圧力で、学習塾・受験費用の捻出が難しくなった家庭が増加。
3-2. 供給側ショック:教育サービスの劣化
- 教員の離職・停職(CDM関連)や学校閉鎖・軍施設化で、授業の提供量が不足。
- 2025年3月の大地震で受験運営に直接の打撃(答案焼失→再試験実施)。
- 地域間の格差(都市/農村、治安状況)により、受験機会の偏りが拡大。
- “二重化”する教育と資格の扱い
- 正規系(国側)のマトリ試験に加え、**代替入試(例:BECAなど)**が登場。
- それぞれの信用・相互承認が未整備な領域があり、大学・企業は評価基準の明確化が求められます。
- 応募者の**「在学・在籍証明」取得が困難**なケースも増加。実務課題や短期トライアルでの評価が有効です。
- 企業・大学への実務的な示唆
5-1. 大学・専門学校
- 出願要件の柔軟化:年齢上限、代替入試・科目履修証明の受理、ブリッジ講座(英語/数学/IT基礎)をセット提供。
- 学力証明の多様化:オンライン試験・ポートフォリオ・推薦文の併用。
5-2. 企業(採用)
- 学歴証明の取得困難を前提に、実技課題/短期有償トライアルでスクリーニング。
- 在留・就業手続きを見据え、雇用前の文書整備テンプレートと**本人側支援(日本語/IT基礎)**を準備。
- オンラインでの職務サンプル確認(Git/設計書/テストケース)が有効。
- 当社(GIC)の支援メニュー
- 奨学金・学習ブリッジ:高校〜大専向けの奨学金支援と、英語/IT/JLPTの短期集中講座。
- 越境進学・就職支援:ミャンマーIT就職フェアの開催・日本企業とのマッチング。
- 企業向け採用設計:学歴証明の代替評価、実技試験・課題作成、OJT受け入れ設計。
- 24/7 運用BPO(英日対応):IT運用・ヘルプデスクを宮崎×ミャンマーのハイブリッド体制で提供。
お問い合わせ:本記事末尾のフォームまたはサイト内「お問い合わせ」からご連絡ください。
まとめ
- 受験者数はコロナ+社会情勢+地震の三重苦で歴史的な落ち込み。2024–25の一時増は再試験効果で、構造的課題は残る。
- 教育制度の“二重化”が進む中、相互承認と評価基準の明確化が重要。
- 企業・大学は、証明書偏重から実力評価への転換を。ブリッジ教育とセットで人材の活路が開ける。
よくある質問(FAQ)
Q1:マトリ試験は大学進学に必須ですか?
A:現行制度では主要ルートです。ただし近年は代替入試や私学ルートが増え、大学側の受理基準が分かれる場合があります。
Q2:受験者数は今後回復しますか?
A:短期的な反発はあり得ますが、治安・教師供給・家計状況次第です。制度の信頼性と学習機会の回復が鍵です。
Q3:学歴証明が出せない応募者はどう評価すべき?
A:実技課題、作品ポートフォリオ、リファレンスなどの代替評価を併用。短期トライアル雇用も有効です。
Q4:日本の学校への出願は可能?
A:学校ごとの要件によります。年齢・科目要件の緩和やブリッジ講座と組み合わせれば受け入れ事例は増やせます。
Q5:企業が今から準備すべきことは?
A:応募要項の明確化(代替証明の可否)、実技評価の標準化、入国・就労手続きのテンプレート整備です。